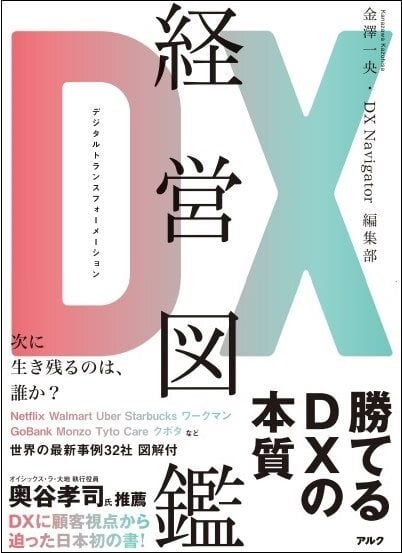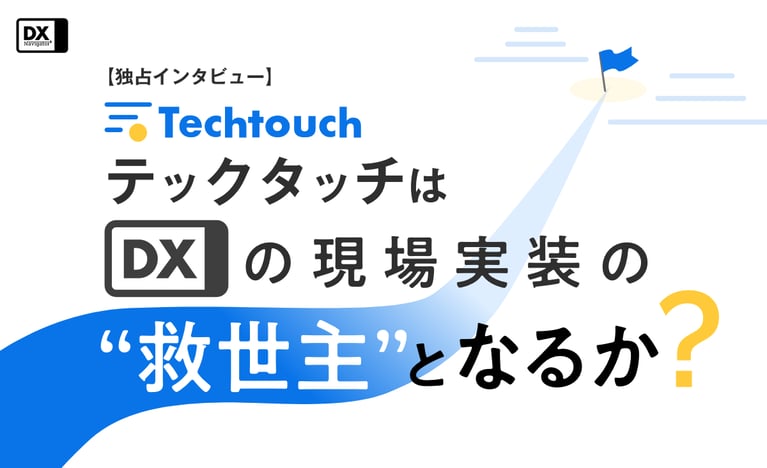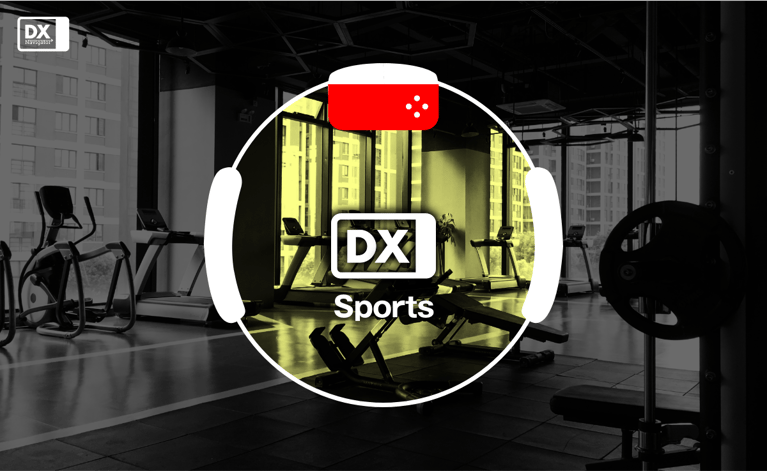序章:NETFLIXED、ディスラプター、DX
日本でNETFLIXを知らない人はもはやほとんどいないだろう。
そのきっかけの多くは「全裸監督」のような話題性たっぷりのコンテンツだったかもしれない。アメリカのドラママニアなら「ハウス・オブ・カード」の虜になったかもしれない。まだコンテンツ契約をしていなくても、プレイステーションやネット対応テレビ、もしくはAmazon Videoでそのロゴを見たことがある人は多いだろう。
そのNETFLIXはいかにして生まれ、成長し、現在の地位を築いたのだろうか?
最近、新潮社から翻訳出版された「NETFLIX コンテンツ帝国の野望―GAFAを超える最強IT企業ー」という書籍がある。元ロイター通信記者である筆者、ジーナ・キーティングの綿密かつ長期の取材に基づいたドラマティックな構成は非常に面白く、まるで映画を見ているような気分にさせる。一方、同書籍の日本語版は2019年6月25日と最近だが、実は原書は2012年に出版されている。すなわち、現在のコンテンツメイカーおよびビデオオンデマンド(以下VOD)企業として成功する前の話までしか書かれていない。なぜ今頃?という不思議な気分になるが、それだけ日本ではNETFLIXが本格的に浸透し、「なぜNETFLIX?」という空気感が強くなってきたということだろう。この7年のギャップが日本と世界(主にアメリカ)のズレとも言えるが、それはまた別の話。
ともあれ、2012年に出版されたこの原書のタイトルは”NETFLIXED”、すなわち「NETFLIX化」である。アメリカのホーム・エンターテインメント市場がNETFLIXによって大きく変化し、市場プレイヤーも消費者もまさにNETFLIX化してしまった、という意味合いである。
私は2016年に渡米しているのだが、その時点でNETFLIXの存在はもちろん知っていた。そして、偶然にも、大学院の授業で課題図書とされたのが原書である”NETFLIXED"であった。何より、コンテンツメイカーとしてのNETFLIXを一躍有名にした「ハウス・オブ・カード」を既にAmazon Fire TV経由で観ていたので、下手な映画配給会社よりも素晴らしいコンテンツを作るVOD(ビデオ・オン・デマンド)の会社、としてNETFLIXを認識していた。そして、ニューヨークに住んでみて、まさに「NETFLIX化」された社会を体感することになった。
地下鉄の駅、工事中の防音壁、42丁目のブロードウェイの看板、いたるところにNETFLIXの新作プロモーションが、ライバルのHBOやFOXと競い合うように展開されていた。ちょうど、NETFLIXはエリザベス2世の伝記映画”The Crown”を、HBOは若きローマ教皇の物語”Young Pope”を推していたので、「米国で言う大河ドラマはヨーロッパの王朝史なんだなあ」と妙に納得したのを覚えている。ともあれ、NETFLIXの登場によってアメリカのホームエンターテイメントはVOD化が大きく進展していた。ケーブルテレビの契約を辞め、ベライゾン(Verizon)のような携帯電話キャリアのブロードバンド環境を引き込み、観たいドラマを観たい時に、観たいデバイスで観ることは極めて一般的になり始めていた。これに合わせて配給会社側も一斉にVODに動き始め、NETFLIXに作品供給する傍ら、他のVOD企業や自前のチャネル充実に力を入れ始め、ホームエンターテイメントはVOD一色に染まりつつあった。これがまさに”NETFLIXED"な社会なのだ。

© Copyright Jaggery and licensed for reuse under this Creative Commons Licence
by Elvert Barnes on Flickr
NETFLIXはそもそも最初から既存ビジネスを破壊するコンセプトでスタートしている。すなわちディスラプターである。イノベーションを起こし、価値提供の仕組みを変えるのがディスラプター(破壊者)の定義とするなら、その手段にデジタル技術を用いれば、デジタル・ディスラプターとも言えるだろう。そして、このニュアンスはDXに酷似している。ほとんどのイノベーションにデジタル技術が組み込まれる現在に置いて、ディスラプターとDXはほとんど同義の言葉と言えるかもしれない。ただ、ディスラプターは既存市場を支配する既存ビジネスモデルの合理化・再構築・破壊によってポジションを築く新興勢力やスタートアップを指すことが普通だろう。一方DXは、ディスラプターに脅かされる既存プレイヤーが、自らのビジネスモデルを自ら破壊することで生き残りを図る行為とも言える。
ともあれ、NETFLIXはディスラプターとして世に生まれた企業である。そしてその歴史の中で、幾度もDXによる自己変革を行い、生き残り、成長してきた企業である。本コラムでは、NETFLIXが破壊してきたビジネスモデルを紹介しながら、何をディスラプト(破壊)し、何をDXしてきたかについて説明していきたい。
1度目のDX(ディスラプト):来店型ビデオレンタルから郵送型DVDレンタルへ
NETFLIXの創業は意外に古い。1997年、サンノゼ(San Jose)市南部の山あいにあるスコッツ・バレー(Scotts Valley)というところで、宅配型DVDレンタルの会社として創業している。初代CEOはマーク・ランドルフ(Marc Randolph)、共同創業者が現CEOのリード・ヘイスティングス(Reed Hastings)である。創業当時、全米におけるレンタルビデオ業界の市場規模は80億規模と言われていた*1。当時、市場を支配していたのはブロックバスター(Blockbuster)である。

TSUTAYA. by MIKI Yoshihito, on Flickr
Geo_Himeji_Tohori_at_dusk
ブロックバスターは1985年テキサス州ダラス創業の業界最大手。当時、地域の中小零細企業が中心だったビデオレンタル店をの多店舗ネットワーク型のビジネスに発展させ、ホーム・エンターテインメントの世界に圧倒的な力を持った巨人である。もともとはローカルなレンタルビデオ店だったが、テキサス州の産業廃棄物管理企業であるWaste Management社のCEOにして、後にマイアミ・ドルフィンズやフロリダ・マーリンズのオーナーとしても知られたウェイン・ハイゼンガー(Wayne Huizenga)が同店舗網を買い取ってから一気に全米拡大。最盛期と言われる2004年には、全世界で従業員60,000人、店舗数は9,000を越えていた*2。ちなみに、ブロックバスターは1991年に日本進出し、1999年には全店舗をゲオに売却して撤退している*3。
この巨人の最大の競争力は新作ビデオの調達力、店舗集客力、そして洗練された店舗設備とオペレーションである。筆者は日本展開時に板橋の店舗を訪れたことがあるが、店舗の明るさや広さ、デザインのかっこよさに驚いたことを覚えている。ブランドカラーの青を基調とした幅の広い通路、ベルトコンベア型のレジ、ビデオと一緒に食べたいスナック菓子やソーダ類の充実ぶりにアメリカを感じた。それまで一般的だった、陰鬱で狭苦しい、まちのビデオ屋とは明らかに一線を画していた。顧客はヒット中の新作ゲットを目指して店舗に向かった。不運にして貸出中なら、返却ラックの前で待つことも、長蛇のレジ待ちも厭わなかった。日本ではこのモデルをTSUTAYAやゲオが踏襲しているのは周知のところである。
ブロックバスターに代表される従来型レンタルビデオモデルは、店舗に来てもらうことが大前提で成立する。人気作を確保して人を集め、返却によって再び来店需要を作る、という黄金ループがベースにある。その黄金ループが習慣化してしまえば、来店の都度、旧作などの「ついで借り」を、レジ前でポテトチップスなどの「ついで買い」といったクロスセルを推奨することで、顧客単価が上がっていく仕組みである。ブロックバスターは、この仕組みを洗練させていき、頂点を極めた。圧倒的な在庫量、特に新作レンタルの調達力と快適でスムーズな顧客動線、清潔な店内、素早いレジワークを提供して店舗体験を最高のものにし、零細ビデオ屋をどんどん駆逐併合して市場を拡大していった。
NETFLIXが創業した1997年は、インターネットの完全商用化(1995年)の2年後である。既にAmazonやYahoo!、eBayは創業しており(いずれも1995年創業)、誰もがインターネットにビジネスの可能性を感じ始めた頃である。創業者であるランドルフとヘイスティングスはインターネットを活用したレンタルビデオビジネスに可能性を見出した。そしてもう一つ。この1997年はアメリカでDVDプレイヤーの商用化が始まった年でもある。
彼らが着想したビジネスモデル破壊のポイントは、来店型店舗モデルの破壊である。これを実現するために、2つの戦略を実行する。一つは、郵送でのレンタル。ユーザーは店舗に行かずにレンタルができる。もう一つは次世代規格であるDVDフォーマットへの特化。かさばるVHSビデオに比べ郵送破損や在庫管理コストを最小化できる。さらに、デジタル媒体なので原則として画質劣化しない。様々なeコマース企業がそうしたように、店舗ビジネスの大前提である「来店」というユーザー使役負荷をゼロにし、必要な店舗体験を可能な限りデジタル上で再現することでユーザーを満足させる。ちなみに、先行しているAmazonは創業当初書籍販売からスタートしているが、その理由は在庫管理が楽(小さく、腐らない)で、郵送が可能なサイズだったからである。NETFLIXが郵送モデルに目をつけ、DVDに特化した背景には、Amazonモデルの転用があったことは間違いない。
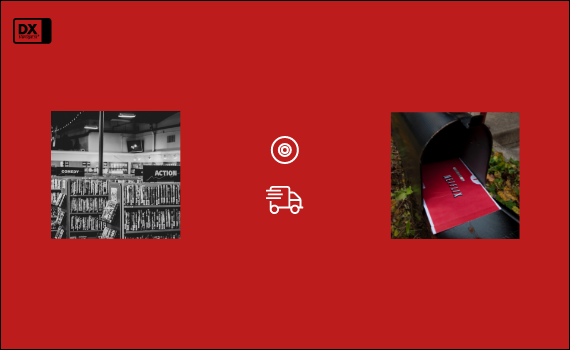
このように、NETFLIXは、無店舗郵送型で店舗型のモデルを破壊し、新規格のDVDレンタルで旧来のVHSビデオレンタルを破壊するディスラプターとして創業した。一方で、彼らがとったニッチ戦略は、彼らの生き残りに一役買っている。オンラインDVDレンタルの専業、という立ち位置は既存ビジネスのリーダーであるブロックバスターに「所詮ニッチプレイヤー」としての油断を与え、創業期に全面戦争となることはなかった。それどころか、実現しなかったにせよ、クロスプロモーション(お互いの顧客をシェアし合う)提携の商談も行われている。DVDプレイヤーの浸透度は当時まだまだ小さく、売上のスケールも主流規格のVHSレンタルには遠く及ばず、大企業にとって旨味のある挑戦ではなかったのである。
また、オンラインの先行者AmazonともDVD販売事業で提携している。まだまだ小さい市場とはいえ、NETFLIXはDVDに特化することで、あっという間にDVDコンテンツの在庫量、そして利用顧客リストNo1の座についた。書籍以外に販売領域を広げたいAmazonはDVD販売に興味を持っていたが、オンラインDVDレンタル最大手であるNETFLIXと競合してお互いに消耗することは得策ではない、と判断した。NETFLIXはターゲット市場を先鋭特化したことで、創業期からブロックバスターとAmazonを同時に敵に回すという驚異を回避できた*4。
2度目のDX: サブスクリプションへの挑戦
ところで、従来型のレンタルビデオ店の重要な収益源の一つは、延滞料金である。出張や旅行で、または返却が面倒になって渋々延滞料を支払った人たちは多いだろう。そして、それこそがレンタルビデオのビジネスモデルにおいて重要な要素の一つであった。人気作を可能な限り早く回転させるために、延滞に高額のペナルティを課すことでチャンスロスを防ぐことが当初の目的だったわけだが、いつの間にか延滞料金が利益の大半を占めるようになった。一説によれば、利益の70%が延滞料金だったと言われている*5。

実はNETFLIX自体も当初は延滞料金をとっていた。よく語られる「CEOのヘイスティングスが『アポロ13』をレンタルしたとき40ドルの延滞料を払う羽目になったのが創業のきっかけ」というのは、どうやら都市伝説らしい*6。ともあれ、NETFLIXは延滞料金という収益源を捨て、サブスクリプション型の収益モデルに軸足を移行する。これを可能にしたのが、「Marquee Plan(マーキー・プラン)」と呼ばれるサービスモデルである。マーキー・プランは、2つの「借り方」を選べる統合プランである。1つは従来型の単品レンタルモデルで、1タイトルごとにレンタル料を支払い、延滞料も発生する。2つ目はホーム・レンタル・ライブラリと呼ばれるもので、月額20ドル払えば同時に6本までレンタル可能。返却することで次の6本が借りられる。延滞料は発生しない。そして、この2つのサービスは、「QUEUE(キュー)」と呼ばれる予約リストと連動する。NETFLIXサイト上のアカウントで観たい映画のリストを作っておけば、返却と同時に次のタイトルが自動送付される仕組みである。ユーザーはピンと来たものをリストに入れておき、観たい順番に借りることができる。返却の都度、次のタイトルが送られてる。返却のたびに「次はどうしようか」と思いを巡らせたり、レンタル単価を気にする必要はなくなる。このマーキー・プランは大成功を呼び、NETFLIXは大幅に新規ユーザーを獲得することが出来た。
一方のブロックバスターもDVDレンタルの取扱を開始した。しかし、サブスクリプション化も、予約のオンライン化にも対応することが出来なかった。売上の大半を占める延滞料金を捨てる決断は難しかったし、なにより、各地域の店長やフランチャイズオーナーからの猛烈な反対にあった。店舗運営者の視点から見れば、NETFLIXのモデル吸収は、ネットに店舗集客を奪われ、かつ延滞料金という収益源を減らすという理解しがたいものだったのである。
NETFLIXがサブスクリプションであり事実上のVODであるマーキー・プラン展開に踏み切ったのは、顧客維持率の向上のためであり、顧客ライフタイムバリュー(LTV)の高値安定のためである。NETFLIXは当時まだまだ赤字体質であり、キャッシュフローの確保は至上命題だった。そして何より、集客要素となる新作の大量仕入れはブロックバスターなどの大手店舗型レンタルには到底かなわない。このため、安価な旧作を可能な限り広く集め、ユーザーに借り続けてもらう必要があった。彼らはキャッシュフローを改善し、生き残るためにDXに着手した。デジタル技術を活用して、提供価値を変えることにした。

もともとのレンタルビデオ事業の顧客価値は、「購入するよりも安価にコンテンツを消費できる」ことと「家庭内在庫を持たなくて済む」ことである。しかし、延滞料というペナルティのおかげで、「買うより安価」という顧客価値は帳消しになる。延滞すれば、買うより高くなってしまうのだ。結果として、顧客はレンタルビデオに期待する価値を変えていく。二度は観ない(かもしれない)コンテンツを家庭内在庫にすることなく、「観たいコンテンツに出会い、消費できる」ことに重きをおくようになった。すなわち「新作調達力」や「旧作在庫のバリエーション」そして「観るべき映画の推奨」など、品揃えとキュレーションに価値を見出し始めた。たとえ延滞料というペナルティがあっても、「観たいコンテンツに出会い、借りられる」ならばよし、ということだ。
NETFLIXはサブスクリプションによって「購入するより安価」というレンタルビデオの根源的な提供価値に立ち返った。代償として延滞料という短期収益が犠牲になるが、顧客の満足度が上がり、会員継続率は確保できる。また、1年以上の長期スパンで見れば月額定額制のほうが収益率が良いと判断したのである。ただし、そのためには「観たいコンテンツに出会い、消費できる」という価値提供プロセスの効率を最大化して、離反を防ぐ工夫に注力しなければならない。彼らはデジタル技術でこれを解決する。
NETFLIXは当時既にDVD在庫ではNo1である。最も豊富な旧作バリエーションを持っていた。そこに「Cinematch(シネ・マッチ)」と呼ばれるリコメンドエンジンを開発し、常にユーザーが欲しがるタイトルを在庫の中から提案しつづけることにした。このループが回れば、不良在庫のリスクは下がり、顧客満足度は上がる。利用が増えるほど、リコメンドの精度はどんどん上がっていく。先述のキュー(予約リスト)のおかげで、「Aを借りた人の90%がBを借りる」という協調フィルタリングの精度が上がっていくのだ。資金面で新作調達力はブロックバスターに敵わないが、「旧作バリエーション」は保有在庫に限界がある店舗型レンタルに対して優位に立てるし、店舗によって差がある「映画の推奨」力はシネ・マッチでカバーできる。キャッシュフローが改善すれば、自ずと新作調達力は強くなる。
彼らがサブスクリプションで軌道に乗れた理由の一つは、ユーザーが「サブスク負けしない」サービスモデルを作れたことであろう。NETFLIXはロングテール需要に対応する大量かつ広範囲なレンタル在庫(アニメやボリウッド、マイナースポーツやインディーズ映画など)をシネ・マッチで推奨し、これらを欠品なく自動配送し続けることで、従来の単品レンタル以上のコストパフォーマンスをユーザーに提供した。少なくとも当時のアメリカにおいて、20ドルで6作レンタルは妥当な値段(当時の相場は新作1本7ドル、旧作は3ドル程度)であり、週に1本以上借りるユーザーならばメリットしか無い。月に6本消化しきれなくても、延滞料がないので、観る時が来るまで家に置いておける。つまり、ユーザーは定額料金以上の価値を感じることができ、「サブスク負け」を感じないのだ。弱点である、新作や人気作の単品需要はブロックバスターに任せておけばいい。事実、この時点で多くのNETFLIXユーザーは地元の店舗型レンタル会員でもあり、店舗型とNETFLIXを使い分けていた。

NETFLIXのサブスクリプションへの挑戦は、ユーザー目線から始まってはいない。むしろ、新作調達力という弱点をマニア向けのロングテール需要で補うビジネスモデルが前提にあり、NETFLIXでのレンタルを習慣化することで安定的キャッシュフローを確保しようという、極めてビジネス視点から始まっている。一方、NETFLIXはこのマーキー・プランを実行するに当たり、入念なユーザテストやインタビューを行うことで、一度に借りられる本数や価格、新作と旧作のバランスなど、ユーザー側のニーズと綿密な照合を行ってからサービスローンチしている。つまり、提供価値と知覚価値のギャップ確認を抜かりなく行っていた。重ねて言うが、NETFLIXはユーザーニーズだけに傾倒している会社ではない。自らの経営課題を解決するために緻密な戦略を打ち、知覚価値とのバランスを常に考慮した結果、彼らのサブスクリプションは世に出された。
そして、2000年、単品レンタルサービスは完全に廃止され、サブスクリプション一本で勝負することになる。この決断もまた、赤字体質脱却のためにサブスクリプションに経営資源を集中するというビジネス視点からのものである。
NETFLIXは何故、サブスクで生き残れたのか
結果的にNETFLIXはサブスクリプションで成功することになるのは周知であるが、ここで、彼らの決断の成功要因をDX視点で見ていこう。
そもそも、ビデオレンタルというビジネスモデルは、サブスクリプションと親和性が高い。利用者は所有するためではなく、コンテンツを楽しむ体験のために対価を支払う点で、サブスクリプションの一つの側面である「所有せず利用する」を最初から満たしているサービス形態である。では、何故ブロックバスターを始めとした伝統的プレイヤーは、最初からサブスクリプションを行わなかったのか?それは店舗型運営だったからに他ならない。
ビデオレンタル店は基本的に自社店舗に在庫を持ち、それを回転させて売上を上げる。店舗間の在庫シェアはあまり行われない。売上と利益を最も上げる方法は、売れ筋商品を確保し、死に筋商品を切ることで面積あたりの販売効率を上げ、不良在庫の滞留率を下げることである。店舗モデルは、売れ筋の欠品は致命的である。新作や人気作は常に店に置かなければならないが、流通量も仕入量も限られる。このため、延滞料というペナルティを課すことで回転率を高め、延滞によるチャンスロスを利益に変える。だが、サブスクリプションを行うとしたらどうだろう。限られた在庫スペースを有効に使うため、単価も高いが仕入れ値も高い人気作の確保を優先し、かつ延滞料という収益を放棄しなければならない。同時に、人気作欠品を補う旧作のバリエーションを確保できないというジレンマに陥る。同時にユーザーは、観るべきコンテンツに出会えないので、定額料金分以上の本数をレンタルできない、という「サブスク負け」が確定するサービスになってしまうのである。
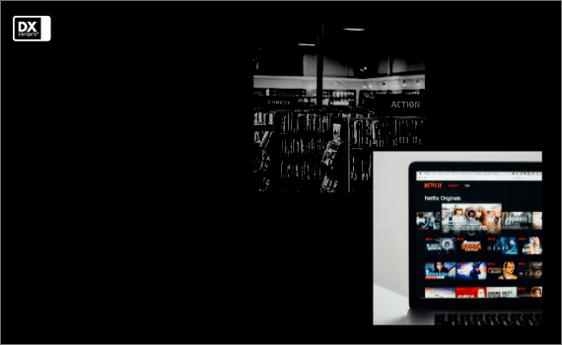
NETFLIXは流通センターに在庫を保管する無店舗型であり、センター間の在庫データは共有されている。ダラスのセンターに在庫がなければ、ヒューストンから送ることも可能である。店舗間のライバル意識や縄張りも存在せず、USPS(アメリカ郵便局)の既存インフラを研究し尽くして、翌日配送が可能な流通プロセスも確立している。このため、店舗型よりも格段に欠品が起こりづらい。逆に資金面での問題があるので、調達にコストがかかる新作・人気作を揃えることは難しいのだが、低コストな旧作のバリエーションを確保し、ニッチなロングテールに集中したことでマニア層の嗜好データを蓄積し、自前のリコメンデーション・エンジンであるシネ・マッチを進化させ、有効に在庫をさばく仕組みを開発した。結果的にこの仕組が強力な参入障壁となり、他社の追随を許さない差別化要因となり、サブスクリプションモデル実行の土台となった。
NETFLIXがサブスクリプションで生き残った要因は下記にまとめられる。
まず第一に、既存収益モデルを自ら捨てて、新しい収益モデルに賭けた「選択と集中」である。
彼らは延滞料収入モデルを捨てた。それだけでなく、創業初期の収益源だったDVD販売も捨てた(1998年にAmazonと提携)。この背景には小規模事業者としての経営資源の選択と集中戦略があるわけだが、ブロードバンド化によって来るべきVODの本格化も見据えてのことだろう。2つの巨人に挟まれる消耗を避けつつ、コンテンツ消費習慣のパラダイムシフトを見据え、これに賭けたのである。つまり、ホーム・エンターテインメントの次世代スタンダードは、店舗に並んで新作をゲットすることでもなく、買って所有することでもなく、観たい時に観たい場所でコンテンツを買う、VODの時代になる。その未来に向かうことに決めたのだ。実際、NETFLIXがサブスクリプションを開始した当時はブロードバンドの浸透が始まり、ビデオ・ストリーミング・サービスが出現していた。回線スピードが上がり、対応コンテンツが増えれば、VOD時代がすぐに訪れる、という空気感は強かった。ブロックバスターもそれに気付いていたが、彼らは既存収益モデルを捨てることは出来なかった。

第二に、「フェアな価値交換」の主張である。
延滞料モデルは、収益構造から考えれば完璧である。売れ筋をメイン商材とし、延滞料で返却率を上げ、かつ収益を確保する。ユーザーはそのペナルティ制度に「やむなく」甘んじてきた。所詮コピー商品の又貸しに高額な延滞料を払うことは納得がいかない。しかし、次回作を借りられないと困るからそうしていた。NETFLIXは自らの新作調達力の脆弱さを逆手に取り、延滞料を本来の姿に戻した。すなわち、収益源ではなく、「次回作を借りるための返却義務」という本来的な位置づけに戻し、その対価としての定額制を打ち出したのだ。延滞料という収益源を犠牲にして、消費者に対してフェアな企業である側面を前面に打ち出した。次が見たいならば返却してほしい。自らの権利のために最低限の義務を果たしてほしい。我々はペナルティという名の収益がほしいわけではなく、正当な価値交換を実現したいのだ、という強力なメッセージである。伝統的ビジネス市場には大抵、アンフェアな価値交換があり、それが大きな収益を生む構造になる。消費者側の選択肢が少ない場合、これは顕著になる。寡占市場では価格が高値止まりするし、売り手に有利な契約が成立する事になるのだ。しかし、技術革新や新規参入が起こったとき、アンフェアな価値交換は攻撃の対象になる。ともすれば暴利を貪る象徴とみなされ、フェアを訴えるサービスに熱狂的信者がつく。NETFLIXは「フェアな価値交換」を訴えることで、巨人ゴリアテと戦うダヴィデの地位を得、熱狂的信者を獲得した。

第三に、デジタルで新しい価値提供プロセスを生み出したことである。
フェアなサービスは聞こえがいいが、多くの場合収益が伴わない。言い換えると、実現が難しいからこそ、アンフェアでも価値交換が成立する。この実現困難な価値提供プロセスをデジタルで可能にするのがDXであるといえる。NETFLIXは、これを実行した。在庫データの一元化、注文翌日配送、返却後の自動配送といった流通スキームを土台にし、高精度のリコメンデーションでユーザーとコンテンツをマッチさせ、予約リストで必要供給量を常時予測し、高速で在庫を回転させ、ユーザーに「サブスク負け」を感じさせない。店舗型運営スタイルでは絶対に実現不可能な価値提供プロセスを作り、既存プレイヤーの参入障壁を高くした。事実、ブロックバスターは後日ブロックバスター・オンラインを設立してNETFLIXとの熾烈な戦いを始めるのだが、オンラインで利益を出すことが出来ず、結局店舗ビジネスに集中することとなり、破産への道を歩んだ。彼らはデジタルと店舗を駆使してNETFLIXと同等以上のサービスを提供したが、持続可能な価値提供が出来なかった。すなわち、デジタルで新しいプロセスを作るには至らなかった。
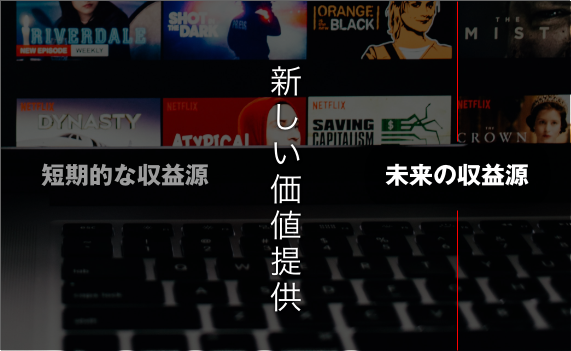
NETFLIXは、ビデオレンタル本来の「非所有型消費」と、フェアな価値交換の対価としてサブスクリプションによる定額支払いをユーザーに求めた。短期的な収益源を放棄して、未来の収益スキームでリーダーになることを目指したといえるだろう。DXには大なり小なりこういった決断が必要だ。そしてそれは必ずしもユーザー視点バンザイというわけではない。自らの資本力や競合とののポジショニングという制約条件を緻密に理解し、その下で提供できる差別化と提供価値の中から、ユーザーが欲する知覚価値との折り合いをつけに行ったのである。そして、それが出来たのは、翌日配送と在庫共有を可能にした流通システムと、滞留在庫を有効にリコメンドできるシネ・マッチ、そして家に居ながらにして視聴リスト作成と決済を完了できるWEBサイトがあったからである。彼らは自らのデジタル資産をフル活用して、生き残りのために自らの価値提供プロセスを変更したのである。
ディスラプターがDXを行うということ
冒頭で述べたように、ディスラプターとDXの定義は非常に近似している。あえて言うならば、創業時点でデジタル前提の市場破壊を目論むことがディスラプト、市場で既にポジションを持っていて、生き残りのために自らの価値提供スタイルをデジタルで変える企業の試みがDXと言えるかもしれない。
NETFLIXは、ディスラプターとして創業し、わずか3年でDXを行った企業である。そしてそれは(次回以降に述べるが)継続的に続いていく。このことは特殊なことではない。AmazonやGoogleもまた、同じことをして巨人と呼ばれるに至っているのだ。デジタルネイティブな企業は、そもそもの始まりがディスラプターである。その中でさらに生き残り、成長する企業は、確実に収益構造や提供価値を変えていく。Amazonは書籍のECからスタートし、品目を広げ、現在の収益の柱はサーバー環境レンタルのAWSである。Googleは当初、Yahoo!に検索のアルゴリズムを提供するところから始め、検索連動型広告という収益源を確保し、現在はデータマネジメントへのシフトを試みている。

ここからわかることは、現代に置いてDXとは生き残りのために不可欠な要素であり、かつ、普通なことである。デジタルのど真ん中に身をおいているいわゆるGAFAですら、何度も収益モデルの変更を模索している。実際、Googleの主要収益源である広告は年々、AmazonやFacebookに迫られており、かつて100%広告依存だった収益が現在は85.5%まで落ちている。Appleはかつて100%プロダクト収益の企業だったが、現在は14%をその他サービス(App StoreやiTuneの手数料、金融サービスなど)で稼いでいる。GAFAの中で一番の後発であるFacebookは未だ収益の98.5%を広告に依存しているが、ザッカーバーグは仮想通貨Libraの成功に全身全霊を注いでいる*7。
彼らは創業当時、あまねくディスラプターだったが、その歴史の中で収益モデルの変更を常に試みている。中でもAmazonのモデル変更は驚嘆に値するが、デジタル広告を席巻するGoogle+Facebook、デジタルデバイスで未だ王者に君臨するAppleらもまた、変化し続けている。(筆者注:彼らのサイズが大きすぎて麻痺するが、例えばFacebookの広告以外の収益源は全体のわずか1.5%でも8億ドル(約880億円)ある)。王者GAFAでさえ安定はなく、常に強烈な競争にさらされており、継続的なDXが必須となっている。顧客は常によりフェアなサービスを欲しており、大きな市場には常にフェアを売り物にしたスタートアップが現れ、いずれ市場のルールを破壊する。世界を席巻するGAFAもまた、変化し続けることを余儀なくされている。
こういった視点から考えるならば、DXの実践は生き残りのための呼吸のようなもので、特別なことではないのかもしれない。少なくとも現在は、そういう時代に入っている。
次回は、NETFLIXの3回目のDX、VOD(ビデオオンデマンド)への挑戦から触れていきたい。
引用情報:
*1 *4 *6
Keating, G. (2012). Netflixed: The epic battle for America's eyeballs. Penguin.
*2
Kovarik, B. (2015). Revolutions in communication: Media history from Gutenberg to the digital age. Bloomsbury Publishing USA.
*3
Wikipedia(2020), Blockbuister LLC, retrieved from
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockbuster_LLC
*5
Christensen, Clayton M.(2012), "How Will You Measure Your Life?” . Harvard Business Review.
*7
Visual Capitalist(2019), How the Tech Giants Make Their Billions, retrieved from
https://www.visualcapitalist.com/how-tech-giants-make-billions/